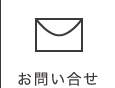NEWS
- お知らせ
外部の実習指導者を招いたオスキーで学生の臨床能力を評価
リハビリテーション学部で10月18日に実施
本学の理学療法学科3年生を対象に11月に実施する臨床実習(評価実習)を前に、学生たちの現在の技術や患者への態度などを評価する「客観的臨床能力試験(通称オスキー)」が10月18日に本学リハビリテーション学部で行われた。
「オスキー」とは、知識面だけでなく、技術面や態度面を点数化することで、実習前の学生の臨床能力を客観的に評価するもの。事前に提示された複数の症例のなかから整形と中枢疾患の2つの課題を無作為に出題。整形では疼痛(損傷などによる痛み)の評価と状況判断、整形外科テスト(疾患の症状や障害部位を特定するための手技)、検査測定の正確性などが求められる。中枢では患者自身ができる能力を判断しながら、それに応じた起居動作や歩行の介助など行うことが求められる。いずれの疾患もリスク管理能力や患者への丁寧な話し方、コミュニケーション能力も問われる。


本学では症例や課題の設定、評価用紙の作成などに毎年改良を重ねながら臨んでいる。模擬患者役は臨床実習で経験を積んで国家試験勉強中の同学科4年生が務めていること。さらに「本学の臨床教員」という立場で外部施設の臨床実習指導者を招いて本学教員とペアを組んで評価や個別指導を行っていることは本学独自の取り組みとなっている。これらにより、より客観的に学生の臨床能力を伸ばすことを重視し、受験生は臨床実習の本番さながらの緊張感が漂う試験会場で実力を試されている。

右脳出血により、体の左側の認識や概念がない「左半側空間無視」の患者の中枢症例を出題された受験生の清水奈緒さん(21)=兵庫県たつの市出身=は歩行の介助をする際に動きがぎこちなくなり、自身の体の位置取りなどに苦しんだ。「普段の勉学では学生同士で確認し合い、疾患についての知識はありました。でも実際の患者さんの状態がイメージできず、介助する時にとまどいました」と反省した。将来は「患者さん一人ひとりに心も体も寄り添える理学療法士になる」ことを目標に掲げる。「体の使い方をもっと勉強して長期実習などで実際の患者さんにも一人で立ち回れるようになりたい」と目を輝かす。
250㏄のバイクに乗って父親とツーリングすることが趣味という小倉海斗さん(21)=兵庫県明石市出身=は「外部の先生のもとでテストを受けたのは初めてで緊張してしまい、練習でできたことも(頭から)飛んでしまった」と頭をかかえた。与えられた症例は「難聴の患者」で「声のトーンによって(言葉の)伝わり方が変わってしまうところが難しかった。経験を積んでいくしかないので、こういう(大学の)取り組みは本当にありがたい」と今度は頭を下げていた。孝行息子は「患者さんに頼られるだけでなく、それ以上に患者さんの家族にも相談してもらえる理学療法士」を目指していく。
臨床実習指導者として参加した大阪市内の病院に務める穴井龍一さん(32)=大阪市出身=は本学の卒業生(2015年3月卒)。「僕が在学中はこういう取り組み(オスキー)はありませんでした。(学生が)勉強しているのが伝わってきたけれど学内の座学だけでは限界がある。外部の指導者が入れば現場のリアルな指摘もでき、学生にとっても臨床実習のイメージが作れて準備もしやすくなる」と本学のオスキーを評価する。卒業して10年が経過。理学療法士として指導する立場にもなり「国家試験に受かり、部分、部分の知識があっても現場に出るとその点と点がうまく重ならない。自分も3年くらいは現場のことが理解できずに苦労しました」と現場の難しさを改めて伝える。それを乗り越えるには「とにかく経験を積むしかない」とし、「学生にとっては実習しかその機会はないので(オスキーを)年に一回ではなく複数回は実施してほしい」と卒業生として後輩への思いを言葉に込めた。