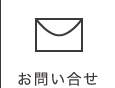教育課程の編成及び実施に関する方針(カリキュラム・ポリシー)
学部・学科のディプロマ・ポリシーを達成するために必要なカリキュラムを、以下に示す教育内容・教育方法・学修成績評価の観点から学部・学科毎に個別に編成します。
- 1. 教育内容
- 専門職業人として必要な知識や技能を修得するために、教養教育と専門教育及び国際性を育む授業科目を体系的に配置します。
- 2. 教育方法
- 授業科目の特性に応じて、教育方法(講義、演習、実習)を適切に組み合わせます。
- 3. 学修成績評価
- 示された達成目標に対する到達度に基づいて、公平で透明な学修成績評価を行います。
経済学部
経済学部では、教養教育と専門教育の履修を通じて、「学力」、「実行力」、「発信力」を修得させるというディプロマ・ポリシーを掲げています。とりわけ、少人数教育である演習科目や共通基盤科目、学科科目を通じ、きめの細かい教育を重視しています。このような方針に従って、学科別・学年別に履修すべき教育内容を以下の通りに定めます。
経済経営学科
教育内容
- ・1~2年次に、幅広い教養を身につける「教養科目」と経済学の基礎を履修させます。
- ・1年次では、高校教育から大学教育へ円滑に移行できるように、「基礎演習」を履修させます。そこでは、大学での学び方と考える力を身につけます。
- ・1年次に、経済学の考え方や基礎知識を修得できるように、「基礎経済」を履修させます。そこでは、経済学の面白さやそれを学ぶ意義について学習します。
- ・2年次は、経済学・経営学の専門基礎知識を広く修得できるように、「共通基盤科目」を履修させます。そこでは、当該分野を専門としない学生でも他の専門基礎を体系だって学習できます。
- ・入門科目・共通基盤科目について「選択必修制度」が定められ、広い分野の科目を体系だって学習できるように、入門科目、共通基盤科目をそれぞれ4群(経済・経営・国際文化ビジネス・観光)の中から、所定の単位以上を履修させます。
- ・入門科目・共通基盤科目を修めた2年次後期以降の学生は、経済学・経営学の専門分野を重点的に修得できるように、「専門科目」を履修させます。そこでは、当該分野の専門知識を深めるために体系立った学習ができます。
- ・3年次から3つのコースを設定し「専門演習」を履修させます。専門演習では特定のテーマで指導を受け、学生自身による主体的学習に基づく報告発表と学生相互の討論を通じ、創造性やプレゼンテーション能力を身につけます。
- ・4年次の専門演習では活動成果を「卒業論文」として提出できます。
- ・キャリア教育科目を1年次から3年次まで設置します。1年次では、将来の仕事への意識付けと就職を希望する業界について、2年次では、アーリーインターンシップを通して企業での働き方を、3年次では、就職を想定したインターンシップを通して仕事の取組み姿勢を学びます。
- ・履修コースモデルを用意し、コースツリーを明示することによって系統的な履修が可能になります。一定の条件を満たした学生を当該コースの修了者と認定します。
教育方法
- (1)演習科目を中心に、少人数の共通教育科目や学科科目、語学科目では、グループディスカッション、ディベート、グループワーク等のアクティブラーニング(AL)を積極的に実施します。
- (2)教室での学修に加えて、地域社会や地域企業と連携し、自ら問題を発見し、問題解決する能力を身につけるプロジェクトベースドラーニング(PBL)を実施します。
- (3)今現在社会生活で生じている問題や現象、例えば、SDGs、IT、AI、防災・減災等に関して、学外の企業や専門家を招へいし、生きた経済学を学習します。
- (4)すべての授業にグローバルな視点を取り入れます。
学修成績評価
- (1)学期末試験だけでなく、その他の学習成果(平常の授業における取り組み、レポート、フィールドワークへの参加、プレゼンテーション能力などを含む多様な能力)を合わせて評価をします。
- (2)課題(試験・レポート等)に対するフィードバックを行います。
- (3)学生が上記カリキュラムを履修していく上で、1年間に履修科目として登録できる単位数の上限を48単位に定めます。
※なお、各科目の学習成果の評価方法は、シラバスにおいて科目ごとに明示されています。
国際文化ビジネス・観光学科
教育内容
- ・1~2年次に、幅広い教養を身につける「教養科目」と経済学の基礎を履修させます。
- ・1年次では、高校教育から大学教育へ円滑に移行できるように、「基礎演習」を履修させます。そこでは、大学での学び方と基本的な考える方法を学習します。
- ・1年次に、経済学の考え方や基礎知識を修得できるように、「基礎経済」を履修させます。そこでは、経済学の面白さやそれを学ぶ意義について学習します。
- ・2年次は、国際文化ビジネスや観光学の専門基礎知識を広く修得できるように、「共通基盤科目」を履修させます。そこでは、当該分野を専門としない学生でも他の専門基礎を体系だって学習することができます。
- ・入門科目・共通基盤科目について「選択必修制度」が定められ、広い分野の科目を体系だって学習できるように、入門科目、共通基盤科目をそれぞれ4群(経済・経営・国際文化ビジネス・観光)の中から、所定の単位以上を履修させます。
- ・入門科目・共通基盤科目を修めた2年次後期以降の学生は、国際文化ビジネスや観光学の専門分野を重点的に修得できるように、「専門科目」を履修させます。そこでは、当該分野の専門知識を深めるために体系だった学習ができます。
- ・3年次から2つのコースを設定し「専門演習」を履修させます。専門演習では特定のテーマで指導を受け、学生自身による主体的学習に基づく報告発表と学生相互の討論を通じ、創造性やプレゼンテーション能力を身につけます。
- ・4年次の専門演習では、活動成果を「卒業論文」として提出します。
- ・キャリア教育科目を1年次から3年次まで設置します。1年次では、将来の仕事への意識付けと就職を希望する業界について、2年次では、アーリーインターンシップを通して企業での働き方を、3年次では、就職を想定したインターンシップを通して仕事の取組み姿勢を学びます。
- ・履修コースモデルを用意し、コースツリーを明示することによって系統的な履修が可能になります。また、一定の条件を満たした学生を当該コースの修了者と認定します。
教育方法
- (1)演習科目を中心に、少人数の共通教育科目や学科科目、語学科目では、グループディスカッション、ディベート、グループワーク等のアクティブラーニング(AL)を積極的に実施します。
- (2)教室での学修に加えて、地域社会や地域企業と連携し、自ら問題を発見し、問題解決する能力を身につけるプロジェクトベースドラーニング(PBL)を実施します。
- (3)今現在社会生活で生じている問題や現象、例えば、SDGs、IT、AI、防災・減災等に関して、学外の企業や専門家を招へいし、生きた経済学を学習します。
- (4)すべての授業にグローバルな視点を取り入れます。
学修成績評価
- (1)学期末試験だけでなく、その他の学習成果(平常の授業における取り組み、レポート、フィールドワークへの参加、プレゼンテーション能力などを含む多様な能力)を合わせて評価をします。
- (2)課題(試験・レポート等)に対するフィードバックを行います。
- (3)学生が上記カリキュラムを履修していく上で、1年間に履修科目として登録できる単位数の上限を48単位に定めます。
※なお、各科目の学習成果の評価方法は、シラバスにおいて科目ごとに明示されています。
リハビリテーション学部
リハビリテーション学部理学療法学科では、ディプロマ・ポリシーに掲げる「人間力」「学力」「協働力」を修得させるために、教養科目・専門基礎科目・専門科目を体系的に編成します。また学んだ知識を活かした資格を取得することを支援します。
理学療法学科
学年別教育内容
1年次
- ・人文・社会・自然科学分野にわたる「教養科目」を履修させ、生命の尊厳を理解し豊かな人間性を持つ理学療法士となるための素地を涵養します。
- ・外国語科目、医学英語教育、海外語学研修、海外施設研修を通して、国際的な視野とコミュニケーション能力を培います。
- ・医療専門職に不可欠な「専門基礎科目」である「基礎医学」を1年次前期から配し、正常な人体の構造と機能および心身の発達について早期に修得させます。
- ・理学療法士の役割や仕事を理解するために、理学療法学概論演習(施設見学実習)を体験させます。
2年次
- ・「基礎医学」科目について、実習を通して理解を深めます。
- ・疾病と障害の成り立ちおよびその回復過程について学ぶ「専門基礎科目」である「臨床医学」科目を設置します。
- ・「専門科目」である「評価学」・「治療学」など理学療法士の基盤となる学びを経て、臨床実習により検査・測定技術の修得を目指します。
- ・理学療法士の役割や仕事を理解するために、理学療法学概論演習(施設見学実習)を体験させます。
3年次
- ・リハビリテーション科学の専門分化に対応した知識の獲得のために「専門科目」を配置します。
- ・これまでに学んだ知識と技能の統合を図るために臨床実習を実施します。
- ・保健・福祉など理学療法に関わる分野を俯瞰できる力を育みます。
4年次
- ・実際の医療現場においてチームの一員として協働し、自律的に問題解決能力を身につけることのできる参加型実習を行います。
- ・授業や臨床実習で関心を抱いた科学的もしくは実践的課題について「卒業研究」で取り組み、論理的思考と創造的探究心を養います。
教育方法
- (1)少人数学生間でのグループワークを積極的に取り入れ、専門的な学修指導とともに生活・進路に関する助言を行います。アクティブラーニング(AL)を中心とした教育方法を用い、知識の修得とともにコミュニケーション能力の向上、他者とのかかわりから生まれる共感力などを錬成します。
- (2)接遇マナー講座・防災意識を高める競技会や研修会・学外でのボランティア活動等を行い医療専門職として不可欠な社会性を高めます。
- (3)学外での臨床実習前に、実技試験・筆記試験を実施して知識の確認を行います。また実習後には、学内で報告会を行い、実習で得た知識を整理し、解決すべき自己課題を認識し、次のステップにつなげます。
- (4)医療専門職としての土台となる基礎医学の修得については、模擬試験を通して到達度を計り、習熟度に応じて丹念に指導をします。また、4年次後期には理学療法士国家試験の合格に向け、集中的な対策プログラムを実施します。
学修成績評価
- (1)学期末試験だけでなく、その他の学習成果(平常の授業における取り組み、レポート、フィールドワークへの参加、プレゼンテーション能力などを含む多様な能力)を合わせて評価をします。
- (2)課題(試験・レポート等)に対するフィードバックを行い、学生の理解度の向上と知識の定着を図ります。
- (3)学外での実習科目については、実習の評定のほか、学内での事前試験や報告会の内容などを総合的に評価します。