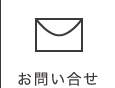NEWS
- 学生の活躍
- 教育・研究
経営者との対話・質問ができる講演会「学びメシ」が開催されました
2024年12月13日㈮経済学部「飲食産業論」の講義の中で“経営者と対話、質問ができる講演会”「学びメシ」が開催されました。
この「学びメシ」は本学学生食堂「スカイコート」を運営する株式会社ORIENTAL FOODSの米田勝栄社長が主催する講演会の形式で、経営者・アスリート等その道の第一線で活躍する人物をゲストとして招き、ゲストと学生らが対話形式で行う講演会です。今回は履修者多数のため講演と質疑応答の2部構成で行われました。



今回は合宿研修や農業体験などができる宿泊施設を長野県塩尻市内で運営する株式会社スタイルプラス代表取締役の村上博志氏が講師として登壇し、これまでの経営者としての経験や自身が大学生であった時代の話などを交えながら講演を行いました。
多くの場合このような講演会やセミナーでは講師の成功体験や目標達成のビジョンを中心に会が進行するものですが、今回の「学びメシ」では人気番組のタイトルになぞらえ「しくじり先生から学ぶ飲食とは?」というテーマのもと、村上氏の失敗談や逆境からの復帰などを中心にした内容が多く語られ、全ての経験を堂々と話す姿に受講した学生らは熱心に耳を傾けました。


次々と受講生が

【受講した学生の感想】※一部抜粋
東日本大震災やコロナ禍など世間が混乱している中でもその状況をチャンスだと考え、その中から何か活かすことはできないのかとプラスに捉える考え方が凄いと感じました。他にも、お客様からのクレームだったり上司から叱られたとしてもその言われたことを自分でどう捉えるかが大事と仰っていました。プラスに捉えることで新しく気づけることがある逆に全てマイナスで受け取ってしまうとだんだん悪い方向に進んでしまうとも仰っていました。私も以前アルバイトでお客様からクレームをもらってしまったことが 1 度あるのですがその時はプラスに考えることはできず2、3日引きづってしまったことがあるので今日の話を聞いて何事もすぐマイナスに考えるのではなく、なるべくプラスに捉えられるようにしたいと思いました。
最も印象に残ったのは、「経営の前提 3つの志向・活動」という内容です。持続可能なビジネスを築くためには、マーケティング(顧客価値を重視したより良い変化)、イノベーション(差別化や独自性を追求する改善活動)、生産性(割安感効率の追求)の 3 つの要素が重要であることを学びました。今回の授業を通じて、ビジネスにおいて持続可能性を追求するには、全体的で長期的な視点が不可欠であることを学びました。この学びは、将来の仕事だけでなく、自分自身の価値観の改善に役立つと思います。 このような貴重な知識を教えてくれたしくじり先生に、心から感謝しています。
会社が潰れたり、お金を横領されたり色々な経験をされても立ち直っているところがすごいと思った。マイナスに思えることもプラスに捉えることで自ら周りの環境をよくしていく姿は勉強になりました。特に東日本大震災の時に何もできなかった反省を生かし、コロナ禍で事業を展開していく話はとても印象に残りました。角度を変えるとものの見方も変わるというのはまさにこのことだと思いました。
村上博志先生の講演を聞いて、マーケティングについて多くの新しい考え方を学びました。特に印象に残ったのは「顧客はドリルを買うのではなく、穴を開けたいのだ」という話です。これは、顧客が本当に求めているものを理解することの重要性を分かりやすく教えてくれました。また、ユニクロの成功例から「商品価値」「購入のしやすさ」「コストパフォーマンス」の 3 つが重要だということを学びました。さらに、「カメがウサギに勝てるレースを設計する」という話も面白かったです。自分の強みを活かし、戦うフィールドを工夫することが大切だと感じました。村上先生の話は具体的な例が多く、とても分かりやすくて勉強になりました。